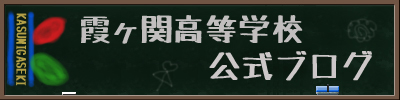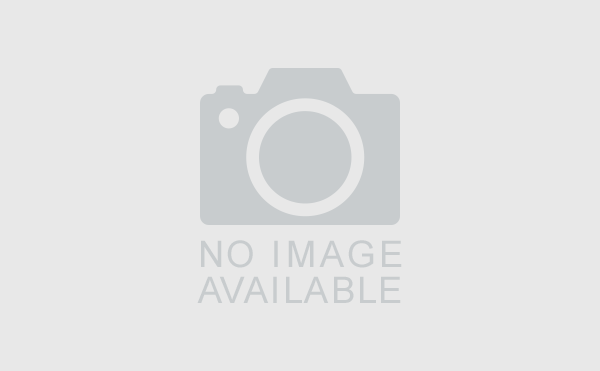[副校長] 職人
『 職人 』
師走二十八日。厳冬の喜多院。早朝にも関わらず、多くの人で賑わっている。この寺で毎月一日だけ開かれる骨董市の日だ。仕事の関係上、私が足を運べるのは、年に数回しかない。小遣いの許す範囲内で気に入った物があると買い求め、得意げに家の者たちに見せては「またゴミみたいなものを買って…」と呆れられている。しかし私にとってこの市は、幾世代も前の職人たちの技と巡り合う事の出来る至福のひと時だ。
陶工に染物師。塗師に細工師。名もない職人たちの作品でも、江戸期のものには技の確かさと仕事の真面目さが伺える。明治期のものには、文明開化の中にあってなお、伝統を受け継ごうという職人たちの意地が感じられる。大正から昭和初期にかけての物には、何処かそれまでの肩の力が抜け、西洋の生産性・合理性を柔軟かつ貪欲に吸収しようという意欲が溢れ出ている。それにしても、木や紙から次々と宝を生み出していく我が国の職人たちの腕と感性は、たいしたものである。
物はその時代の人々の暮らしや精神を映す鏡だ。また、職人たちもその時代に生きていた。だとすると、江戸期までは職人達が物と向き合うのと同じ姿勢を、身分に関わらず人々は己の内に持っていたのではないか。つまり己の技を磨くこと、真面目に物事に向き合うこと、そして身近にあるものから宝(幸せ)を生み出すことを、日々の暮らしの中で静かに営んでいた。しかし、明治・大正・昭和へとj時代が進むに従い、技や真面目さよりも、世界的な消費システムの中で、安く・簡単に・大量に手に入るものに価値を置くことが世の趨勢となっていった。身近にあるものに幸せを見出す日本人の美徳も、いつしかこのシステムに飲み込まれて行った。
骨董とは、およそ百年の時を経た物にその資格が与えられるのだそうだ。だとすると、大正・昭和期の物も続々とその仲間入りをする時期が来ている。しかし、昭和後期や平成時代のものたちが、いずれ自動的に骨董として認められるようになるかは疑問である。せめてわれわれ人間は、己をしっかりと磨き上げ、良い時を刻んで、中古やゴミと呼ばれぬよう、「自分づくりの職人」であり続けたい。
数十年後、諸君が骨董の資格を与えられる頃、鑑定士に「いい仕事して来ましたねぇ~」と唸らせる程の品となっていることを願っている。
2020年5月18日 (以前の自著を一部改編)
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠