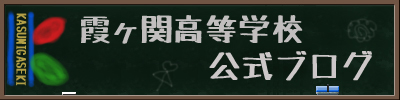[副校長] 蒼い季節(とき) ③
『蒼い季節(とき) ③ 』
高校卒業後2ヶ月程して運転免許をとった。「初めてのクルマはスカイラインか、スープラ」と決めていたはずなのに、最初の愛車は親の乗っていた4ドアのカローラだった。エアコンもパワーウインドーも無かったが、自転車よりは明らかに行動範囲が広がるその乗り物は、「大人」の仲間入りした証にも思え、とりあえず嬉しかった。カーステレオの代わりに、リアシートに積んでいた大きなラジカセから松田聖子の「白いパラソル」が流れていた。大学生の夏が始まった。
2ヶ月以上ある大学の夏休み。バイトもサークルの集まりもない日は、日中家でごろごろして、日が西に傾きだすと庭でクルマを洗った。洗いたてのそいつを夕日が沈むころ、友達を拾って(もしくは一人で)行くあてもなく走らせる。白いボンネットに写った夕日が、赤から紫に変わっていくのを眺めるのが好きだった。
そんな夕暮れ時、中学や高校時代の同級生で浪人していた連中を何度か見かけた。たぶん夏期講習の帰りだろう、重そうなリュックを背負って高校時代と同じ人力の乗り物を、大粒の汗をかきながら漕いでいた。そんな連中を横目で眺めては、少しばかりの優越感を味わったりもした。
思えば高3の夏休み直前、先生から「お前みたいな奴は受からない。保証する」と言われたのに奮起し、夏の30日間ほぼ毎日16時間近く机に噛り付いた。おかげで、2学期の成績は急上昇したものの、それに満足した俺は、また元の生活に戻り受験を迎えてしまった。しかし、考えてみれば、あの夏の16時間勉強は日頃1時間程度しか家庭学習をしない自分にとって16×30=480時間、なんと1年間分以上の勉強をしたことになる。あの時先生の一言がなかったら、今頃俺も自転車組の一員だったかもしれない。いや、たいして根性のない俺では、受験を諦めてしまったに決まっている。
しかし、今の現実に俺は本当に満足なのだろうか。浪人生を見て正直眩しさも感じていた。彼らの中には、志望校を妥協せずに浪人した者も多くいたのだ。俺は浪人せずに生温い大学生活に浸っている。けど、この生活は、流されるまま人生に折り合いをつけて満足しようとしているだけで、あるべき人生に挑戦しない者の典型的姿ではないのか。彼ら自転車組は、自分で立って自力で前に進んでいるのだ。
そんなことを考えながらのドライブは、いつもよりも日が沈むのが早く感じられ、紫から墨色に変わって行く闇を切り裂こうと、決まってアクセルを強く踏み込んだ。
ラジカセからは、ヤンキー風ロックグループの横浜銀蝿が「どうでもイイジャン!!」と怒鳴っていた。
2020.4.3(過去の自著を一部改編)
霞ヶ関高等学校
副校長 伊坪 誠